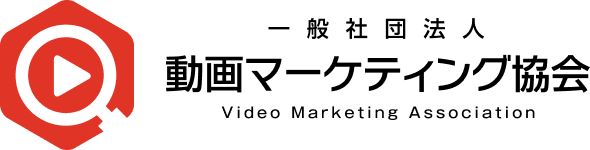2025年7月。静かに、しかし確実に、動画業界の風向きが変わりました。
YouTubeが公式に発表した“AIスロップ動画”への規制は、動画制作に関わる多くの人々にとって無視できないニュースだったのではないでしょうか。
スロップ動画、それは、AIの音声合成、無料素材の切り貼り、テンプレート化された構成を用いた「誰でも」「簡単に」「早く」作れる動画たち。今まで、これらは一定の再生数と広告収益を見込める“お手軽ビジネス”として、一部の副業勢やスモールビジネスに支持されてきました。
しかし、そんな「大量生産型動画」の時代が、今まさに終わろうとしています。
第1章:AIスロップ動画とは?便利さの裏にあった“中身のなさ”
まず、そもそもスロップ動画とは何か。
英語の“slop”は「残飯」や「価値のないもの」という意味を持つ単語です。それが転じて、YouTubeなどに投稿される「AIで作られた中身のない量産動画」を「スロップ動画」と呼ぶようになりました。
スロップ動画には、次のような特徴があります:
• AIが書いた文章を、そのまま合成音声で読み上げるだけのナレーション
• 有名人の写真やフリー素材動画を繋げただけの構成
• 台本、演出、編集、ナレーションすべてにおいて“人の手”を感じさせない機械的な作り
このような動画は、一見情報量があるように見えても、実際には価値ある知識や感情的な訴求が薄く、視聴者の満足度は極めて低い傾向があります。
第2章:YouTubeの動き:収益化対象からの除外
そして、2025年7月15日。YouTubeが発表した新ポリシーにより、スロップ動画に該当するコンテンツはYouTubeパートナープログラム(YPP)による収益化の対象外となりました。
YouTubeは明言しています:
「反復的でオリジナリティのない動画、特にAIなどを用いて自動的に作られたものは、収益化の対象とはなりません。」
これは明確なメッセージです。
「人間が作った、創意工夫あるコンテンツを評価する」。
動画の“質”が問われる時代が、いよいよ本格的にやってきたということです。
第3章:動画編集業界への影響:勝ち残るのは誰か?
では、この規制によって動画制作会社や編集者はどう変わるのでしょうか?
結論から言えば、“動画業界は二極化”していくと考えられます。
一部企業にとっては“死活問題”
これまで「低価格」「短納期」「テンプレ編集」で大量の案件をさばいてきた編集代行業者にとって、この変化は致命的です。
「AIナレーションで安く作ります」
「記事をコピペして5分動画にします」
こういった売り方が、通用しなくなったからです。
結果として、低単価動画を請け負っていた編集者・フリーランスの一部は、案件激減という事態に直面しています。
一方、伸びる企業もある
その逆に、“オリジナリティと品質を武器にしてきた制作会社”はむしろ追い風を受けています。
たとえば:
• 撮影から編集まで一貫して行い、人の表情や感情を大事にしている企業
• ナレーターを起用し、企画・構成にプロの手が加わっている作品
• 映像と音声、BGMに至るまで“世界観”が設計されたプロモーション動画
こういったコンテンツを作っている会社には、法人や自治体からの案件がむしろ増えてきているのです。。
第4章:“人の手”が作る動画の価値
ある編集者はこう語っていました:
「やっと時代が、自分たちの仕事に報いてくれるようになってきた。」
動画制作とは本来、単なる“手作業”ではありません。
企画を練り、伝えたいメッセージを構築し、表現方法を選び、画や音に反映する。そこには確かな“思考”と“感性”が必要です。
視聴者も変化に気づいています。
「AIの声はどこか冷たい」
「テンプレ動画ばかりでつまらない」
そんな声は、ここ数ヶ月で本当に増えています。
第5章:動画制作会社が今すべきこと
これからの時代を生き抜くために、動画制作企業は何を強化すべきなのでしょうか。ポイントは4つです。
① 企画力と構成力の強化
• シナリオが面白くなければ、どれだけ綺麗な映像でも飽きられます
• 視聴者目線で「なるほど」「笑える」「心が動く」構成が不可欠
② 人の声・人の出演を積極活用
• 合成音声から“人間のナレーション”へ
• 顔出しNGでも、インタビューや対話形式の音声は信頼感を生む
③ 法的リスク対策の徹底
• 著作権、肖像権、音楽使用許可などの整備
• 制作物の利用範囲・契約内容の明文化はマスト
④ 専門性の明確化
• 採用動画に強い会社
• 教育・研修動画を得意とする会社
• 医療・士業などニッチ分野の知見を持つ会社
それぞれの“得意分野”に特化し、単なる「編集屋」ではなく「提案型のパートナー」になることが重要です。
これからの動画業界はどうなるのか?
今後、動画の世界はますます「本物志向」へと向かっていくでしょう。
• AIが何でも代行する時代だからこそ、「人の手で作られた動画」に価値が戻ってくる
• 収益化は“コンテンツの質”次第という風潮が強まる
• 法人案件は「信頼できるプロフェッショナル」に集中する
つまり、「安さ・速さ・AI任せ」から、「信頼・創造・人間性」へと軸足が移ったというわけです。
最後に:今こそ、“本当の動画クリエイター”になるとき
今回のスロップ動画規制は、単なるプラットフォームの仕様変更ではありません。
これは、「動画コンテンツの在り方」に対する社会的な問いかけでもあるのです。
あなたが今まで作ってきた動画は、誰かの心を動かしたでしょうか?
視聴者に何かを伝える力があったでしょうか?
「編集技術だけ」では、もう通用しない時代がやってきました。
これから求められるのは、“伝える力”と“考える力”を備えた動画クリエイターです。
あなたの動画にしかできない表現を。
あなたの企業にしか作れない価値を。
今こそ、それを社会に示すときです。
「動画マーケティング協会」は、動画制作に関する同業種のお悩み解決のための組織です。
「動画制作、マーケティングに関係する人と繋がりたい!」
「業界の最新トレンドに触れたい!」
「業界の管理体制が知りたい!」
「営業を強化したい!」
こんなお悩みを抱える皆さんはぜひ動画マーケティング協会へ!
▶動画マーケティングについての情報はこちら!
https://vma.or.jp/join