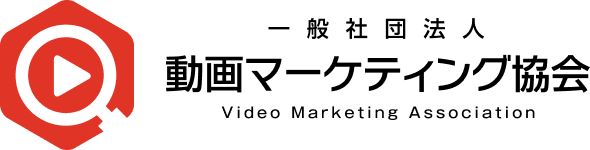1. YouTubeが「最初に観るテレビ」になった理由
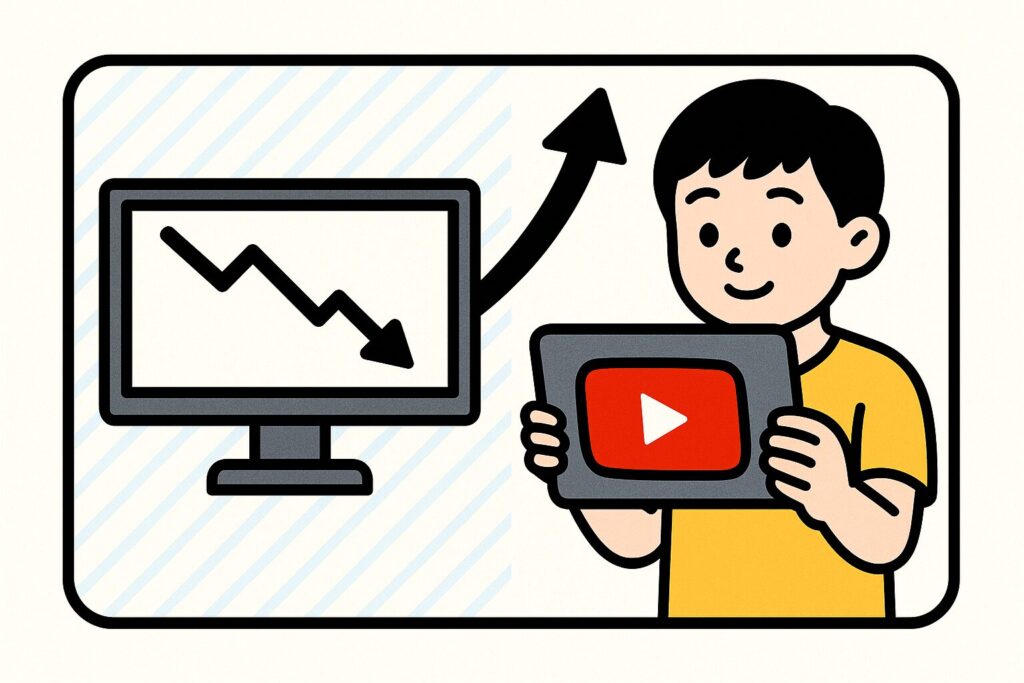
いまやテレビをつける前にYouTubeを開く──そんな光景が当たり前になってきました。特にZ世代やα世代の子どもたちにとって、テレビのリモコンについている「YouTubeボタン」は、最初に触れる“テレビの入り口”です。
イギリスの通信規制機関・Ofcomの調査では、4~15歳のうち20%が「最初に観るのはYouTube」と回答。NetflixやBBC Oneを超える割合です。これに象徴されるように、YouTubeはテレビと並ぶ存在ではなく、もはや“テレビのデフォルト”なのです。
スマートテレビの普及も拍車をかけました。YouTubeは子ども専用のコンテンツを豊富に備えており、保護者からも“安心して見せられる媒体”として選ばれています。
2. テレビ離れは全世代で進行中
若年層だけがテレビから離れているわけではありません。60代以上の世代でも、YouTubeの平均視聴時間は年々伸び続けています。
たとえば55歳以上の視聴者では、YouTubeの1日あたり平均視聴時間が6分から11分へと倍増。テレビが“団らんの中心”だった時代から、“個々のデバイスで自分の観たいものを選ぶ”時代へと、生活スタイルそのものが変化しています。
特に、16〜24歳の世代ではテレビ視聴時間は1日たった17分。週に一度もテレビを観ない割合は45%にも上ります。
テレビのリビング支配は終焉を迎えつつあるのです。
3. YouTubeの“テレビ化”はどこまで進んだか

YouTubeの中身を見れば、すでに“テレビ番組と変わらない”と感じる方も多いはずです。実際、以下のような番組形式が人気を集めています:
- ・トーク番組風のインタビュー動画
- ・ドキュメンタリー風のルポコンテンツ
- ・ニュース解説や社会問題の紹介
- ・ゲーム実況、教育系コンテンツなど
さらに、YouTubeは“音声メディア”としても進化しています。ポッドキャストやラジオ風の長尺動画も普及し、SpotifyやApple Podcastを上回る再生数を記録するケースも珍しくありません。
テレビと同じように視聴者の“習慣”となった今、YouTubeは「映像の新しい標準フォーマット」としての地位を確立しつつあります。
4. 放送局の課題と転換点
英国のBBCやChannel 4などは、すでにYouTube展開を強化し、自社ブランドを守る施策を取っています。しかし、以下のような課題も抱えています。
- ・広告収益の主導権がYouTube側にある
- ・自社アプリやプラットフォームへの誘導が難しい
- ・ブランディングやUI設計に制約がある
そのため、YouTubeを単なる“配信先”ではなく、「広報・導線・トリガー」として位置づけ、自社経済圏(アプリ・サブスク)へと引き込む戦略が求められます。
この構図は、個人で発信しているYouTuberにも同じく当てはまります。自分のコンテンツを“終点”にせず、他の収益モデル(講座、グッズ、サロン、メディアなど)に連携させる視点が鍵です。
5. テレビ局がYouTube発信者から学ぶべきこと
いまやYouTuberの中には、テレビ業界出身者に匹敵する編集力・企画力を持つ人が続々と登場しています。
テレビ局がYouTube発信者から学ぶべきことは以下の通りです:
- ・スピード感のある制作体制(企画→撮影→編集→公開の高速ループ)
- ・トレンドを即座に反映できる柔軟性
- ・ターゲットに絞ったコンテンツ設計
- ・コメントやアナリティクスからの“フィードバック学習”
逆に、テレビ局には「調査力」「検証力」「信頼性」「構成力」といった強みがあります。これを生かして、YouTuberとの共創モデルを築くことが、今後のメディア価値向上の鍵になります。
6. プラットフォーム共存時代の戦い方

視聴者は、テレビとYouTubeを“選ぶ”のではなく、目的別に“使い分ける”時代にいます。つまり、両者は競合ではなく、補完関係なのです。
YouTuberも「テレビ的な信用」を武器にしたり、「深掘り型コンテンツ」を提供することで、より強い関係構築が可能になります。
共存戦略の例:
- ・YouTubeで「導入編」を配信 → 詳細は有料動画や外部講座で
- ・テレビ的な取材ノウハウを生かしたコラボ動画
- ・YouTube Shorts → 長尺コンテンツへの誘導
- ・生配信 + ショート切り抜き → アーカイブで収益化
コンテンツを“マルチプラットフォーム展開”する視点が、YouTuberにもテレビ局にも求められます。
7. YouTuberが生む“新しいメディアのかたち”
YouTuberの中には、もはや“番組の一部”ではなく“メディアそのもの”を担っている存在もいます。たとえば:
- ・ニュース系YouTuberが社会問題を深堀りし、行政やNPOと連携
- ・教育系YouTuberが自治体と地域教材を共同制作
- ・エンタメ系YouTuberがTV番組より多くの視聴数を獲得
こうした動きは、従来のメディア構造を大きく変えつつあります。
YouTubeは「誰でも番組を作れる」時代の象徴です。企業や放送局が参入するのは当然であり、視聴者が“誰から学び、誰を信頼するか”を能動的に選ぶ時代になった今、強い個人や少人数チームが、新しい時代の“放送局”となる可能性を秘めています。
8. まとめ:選ばれるコンテンツを届ける時代へ
かつてテレビは、家庭に1台の“窓”として、多くの人々に情報や娯楽を届ける唯一の手段でした。しかし今、YouTubeをはじめとする動画プラットフォームの登場により、発信の形も、受け取り方も大きく変わりつつあります。
私たちはいま、情報があふれる時代に生きています。数あるコンテンツの中から、どの情報を信じ、どの動画を視聴するかは、完全に“視聴者の選択”に委ねられるようになりました。
だからこそ発信者には、「どこで配信するか」以上に、「なぜこの内容を届けるのか」「誰のために発信するのか」といった、本質的な設計力が求められています。
動画のクオリティ、内容の信頼性、視聴者との距離感──そういった要素のすべてが積み重なって、ようやく「選ばれるコンテンツ」になります。
また、テレビであれYouTubeであれ、問われるのは結局「人」。
視聴者は、“何を言うか”以上に“誰が言うか”を見ています。
つまり、発信者の姿勢や価値観、そして誠実さが、あらゆる時代で変わらない本質なのかもしれません。
どんなメディアが主流になろうと、私たちが忘れてはならないのは、「誰に」「なぜ」届けるのかという視点です。
それさえ見失わなければ、変わり続けるプラットフォームの中でも、自分らしい発信を続けていけるはずです。
「動画マーケティング協会」は、動画制作に関する同業種のお悩み解決のための組織です。
「動画制作、マーケティングに関係する人と繋がりたい!」
「業界の最新トレンドに触れたい!」
「業界の管理体制が知りたい!」
「営業を強化したい!」
こんなお悩みを抱える皆さんはぜひ動画マーケティング協会へ!
▶動画マーケティングについての情報はこちら!
https://vma.or.jp/join