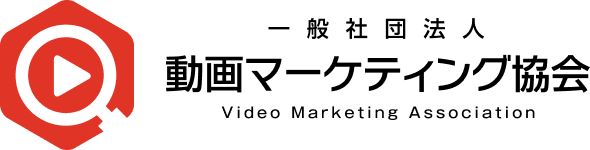はじめに
2020年代前半、SNS界を席巻したのは間違いなく「ショート動画」でした。TikTokを皮切りに、Instagram Reels、YouTube Shorts、さらにはTwitterやPinterestまでもがショート動画機能を導入。あらゆるSNSが“縦動画中心”の設計に変わったのがこの数年の流れです。
しかし、2025年の今、そのトレンドにも徐々に“飽和”の兆しが見え始めています。
ユーザーからは「似たような動画ばかり」「スクロールが疲れる」「もっと深い情報が欲しい」といった声も増えつつあり、「ポスト・ショート動画時代」に向けた新たな潮流が生まれつつあるのです。
本記事では、ショート動画の次に来ると予測されるSNSの形、そしてそれを牽引するテクノロジーやユーザー心理の変化について、深掘りしていきます。
ショート動画の限界とは?5年間で何が起きたか
まず、なぜショート動画がここまで成功したのか、そしてなぜ次のフェーズへと移行しようとしているのかを整理しましょう。
成功要因
• スマホとの親和性(縦型・短時間)
• コンテンツ量産のしやすさ
• アルゴリズムによる“バズ”の民主化
• 若年層によるトレンド牽引(Z世代中心)
これにより、TikTokでは“無名”でも一夜で10万再生される可能性があるなど、夢のある時代が生まれました。しかし、成功が一般化したことによって、以下のような「限界」も見えてきたのです。
限界と課題
• コンテンツの質の均一化(同じダンス・同じネタ)
• 視聴疲れ(エンドレススクロールによる情報過多)
• SNS全体が「軽すぎる」印象に
• 収益化の難しさ(特に短尺動画では広告単価が低い)
このような背景から、ユーザー・企業・プラットフォームの三者が、“次のSNS体験”を模索するフェーズに入ってきています。
動画SNSの未来を担う5つのキーワード
2025年以降、ショート動画に代わる新しい体験として注目されているのが、以下の5つの方向性です。
1. 中尺動画(3〜10分)の復権
YouTubeでのトレンド変化やTikTokの10分動画対応からもわかるように、「少し深い情報」を求めるユーザーが増加しています。単なるエンタメではなく、スキル習得・ストーリーテリング・レビュー解説など、中尺の“学び・発見”コンテンツが再評価されているのです。
特にYouTubeは、中尺〜長尺に強い収益化システムを持っており、クリエイター側にとっても安定収入につながります。TikTokでも2025年現在、「教育系インフルエンサー」や「ビジネス解説系」が伸び始めており、エンタメ一辺倒から“実用志向”へのシフトが明らかです。
2. ライブ×動画のハイブリッド型
ライブ配信も再び注目されていますが、ただの生配信ではなく、「ライブ+事前収録」のハイブリッド型に人気が集まっています。
たとえば:
• ライブ中に、事前に編集した解説動画を挿入する
• 視聴者の反応をもとに、ライブ内で新動画を生成する
• ライブで撮影した映像を即編集・即投稿できるシステム
これは、リアルタイム性の“熱”と、動画編集の“わかりやすさ”を融合させる形。メディア企業や教育系チャンネルなどが積極導入しており、今後さらに拡大すると見られています。
3. AI生成コンテンツ(Generative Video)の普及
生成AIの進化により、動画の自動作成が一般ユーザーにも可能となりました。キャラクター生成、音声合成、ナレーション、BGM自動選定など、すでに多くの無料ツールが存在しています。
これにより起きている変化は2つ:
• 動画投稿の“心理的ハードル”が下がる
顔出し不要、機材不要、編集不要の時代へ。
• コンテンツジャンルが爆発的に多様化する
アニメーション、ニュース要約、バーチャルYouTuberなど、新しいジャンルが続々と生まれています。
今後は「人間が撮影する動画」と「AIが作る動画」が混在する世界が当たり前になると予想されます。。
4. コミュニティ重視型SNSへの移行
情報が溢れすぎている今、ユーザーは「どこでも見られる動画」ではなく、「誰と見るか」「誰の発信か」を重視するようになっています。その結果、小規模でも熱量の高いコミュニティを持つSNSが台頭してきました。
例:
• Discordで限定動画を共有
• Redditでジャンル特化型の動画ディスカッション
• Telegram内だけで公開される限定コンテンツ
つまり、プラットフォームというより「環境」で動画を楽しむスタイルが広がっており、“パブリックからクローズドへ”という大きな潮流が起きています。
5. メタバース・空間共有型SNS
最後に、ショート動画とは全く異なる次元の進化として、「空間型SNS」が挙げられます。
動画ではなく、“空間ごと共有する”体験。
例:
• 3D空間で他人と一緒に動画を観る(Spatial、Meta Horizon)
• アバターでリアルタイムに反応し合いながら交流する
• 自分の作った空間内で動画を流す、演出する
これは従来の「視聴体験」に革命をもたらし、エンタメ性・ゲーム性・交流性を同時に味わえるSNSとして注目されています。
ショート動画は“終わる”のか?
ここまで「ポスト・ショート動画」について論じてきましたが、ショート動画が消えるわけではありません。むしろ、動画SNSの“入口”としての機能は今後も強い影響力を持つでしょう。
ただし、重要なのは「ショート動画=万能」ではなくなったという点。
ユーザーが「気軽に見る」「楽しむ」だけでなく、「学ぶ」「つながる」「表現する」ための選択肢を求めていることが明らかになってきているのです。
まとめ:次のSNSは「深さと共感」が鍵になる
2025年、ショート動画時代はひとつの完成を迎え、次のステージへと向かっています。
• 中尺動画で“深い学び”を得たい人
• AIで動画制作を“民主化”したい人
• クローズドコミュニティで“濃い関係性”を築きたい人
• ライブ配信で“リアルな熱量”を感じたい人
こうした新しいニーズを満たすSNSが、今後の主役になっていくことでしょう。
「動画マーケティング協会」は、動画制作に関する同業種のお悩み解決のための組織です。
「動画制作、マーケティングに関係する人と繋がりたい!」
「業界の最新トレンドに触れたい!」
「業界の管理体制が知りたい!」
「営業を強化したい!」
こんなお悩みを抱える皆さんはぜひ動画マーケティング協会へ!
▶動画マーケティングについての情報はこちら!
https://vma.or.jp/join