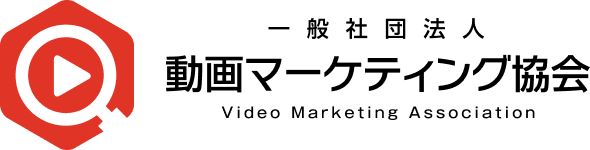第1章:なぜ今、BtoBでも動画コマースなのか(意義)
近年、BtoBビジネスにおいても購買行動のデジタル化が進み、動画を活用した営業・マーケティング手法が注目されています。従来は展示会や対面営業を通じて行っていた製品説明や訴求活動も、オンライン上で効率よく展開できるようになりました。
特に動画コマースは、単なる視覚的な情報提供を超え、視聴者が動画内からそのままアクションを起こせる仕組みを取り入れることで、製品理解から問い合わせ、資料請求、場合によっては購入申し込みまでを一気通貫で促進することが可能です。
加えて、製品の使用感や導入効果を実感として伝えられるため、複数人が関わる意思決定プロセスにおいても、動画が「社内共有用コンテンツ」として活躍する場面が増えています。近年のビジネス環境では、DX(デジタルトランスフォーメーション)や働き方の多様化により、営業・広報・カスタマーサクセスなどの業務にも大きな変化が起きており、動画活用によってこれらの変化に柔軟に対応できる企業が優位に立つ傾向が強まっています。
さらに、若年層の意思決定関与やリモートワークの定着により、オンラインでの製品理解と社内での合意形成を円滑にする手段として動画の価値は高まっています。購買プロセスの情報源として、テキストやPDF資料に比べて短時間で要点を把握できる動画は、社内稟議を通すための説明ツールとしても重宝されています。
第2章:BtoB向け動画コマースの実践ポイント(実践)
1. 製品紹介+CTA導線の設計
YouTubeの概要欄や固定コメント、カード機能などを活用し、視聴者がそのまま資料請求・商談予約・ECサイト遷移できるCTAを明示します。動画内でもナレーションやテロップで行動を促すことで効果が高まります。また、CTAの設置箇所やタイミングについても、A/Bテストを行い最適化することが望まれます。
特に重要なのは、CTAの文言と視認性です。たとえば「今すぐ資料請求」「この製品の価格をチェック」など、アクションを明確に促す表現を使用することでクリック率を高められます。さらに、ランディングページへの導線も含め、全体のUXを設計することが成約率向上に繋がります。
2. 比較動画やユースケースの導入
他社製品との機能比較や業種・業界別の導入事例など、視聴者の「自社に合うか」という疑問に応えるコンテンツが重要です。実際の使用場面を交えたユースケース動画は、導入後の活用イメージを具体化できます。特に導入前後の業務改善効果や、定量的な成果データを組み合わせることで説得力が増します。
また、導入企業の声やインタビューを取り入れることで、視聴者にとっての信頼性が向上し、同業種・同規模の企業に対する訴求力が高まります。ユーザー目線で語られるリアルな意見は、テキスト事例以上に視聴者の関心を引き、エンゲージメントを高めます。
3. ライブ配信での商談化
ライブ配信を活用すれば、製品説明に加え、チャットを通じたリアルタイムの質疑応答も可能です。セミナー形式で見込み顧客を集客し、その場での商談予約やフォローアップ導線を設計することで、即時のコンバージョンも狙えます。加えて、ライブ配信のアーカイブを編集して短尺動画として再活用することで、コンテンツ資産の拡張も図れます。
さらに、ライブイベントには「臨場感」や「参加型コンテンツ」の魅力があります。事前アンケートの実施や投票機能の活用により、参加者の興味関心に応じたセッション構成を行うと、視聴体験の満足度が向上し、ブランドエンゲージメントにもつながります。
4. カスタマーサクセスとの連携
導入後の運用支援や活用方法の紹介も動画で行うことで、既存顧客との関係強化にも繋がります。FAQやメンテナンス手順を動画で提供することにより、サポート工数の削減や顧客満足度の向上が期待されます。また、アップセル・クロスセルを目的とした新機能紹介や成功事例の共有も、動画を通じてスムーズに実施可能です。
とくにBtoB領域では、継続利用や定期契約が重視されるため、契約後も継続的に価値提供する姿勢が求められます。動画による定期フォローや活用レポートの可視化などを通じて、顧客ロイヤルティの向上と解約率の低減を図ることができます。
第3章:効果指標と注意点(指標と注意点)
効果指標
- 動画経由でのコンバージョン数(資料請求・問い合わせ・見積依頼など)
- 視聴完了率や平均再生時間
- CTAクリック率
- 商品別の再生回数や視聴後の行動ログ
- 動画経由で取得したリードの商談化率・受注率
- 動画視聴後のWebサイト遷移率やページ滞在時間
- 再生地域・業種ごとのセグメント分析結果
注意点
BtoBにおける動画コマースは、必ずしも”即購入”を前提とするものではなく、あくまでリード獲得や商談化への導線設計が主軸となります。そのため、動画内の情報設計は、決裁者や技術担当者に納得感を与えるような、スペック・事例・実績に基づいた論理的な構成が求められます。
また、YouTube上での動画展開においては、SEOや動画タイトル、サムネイル設計、概要欄のキーワード最適化も成果に大きく影響します。さらに、モバイルユーザーへの配慮として、音声なしでも内容が伝わる字幕やアニメーションの工夫も必要です。
制作コストや内製化体制の整備も重要な要素です。社内で対応が難しい場合は、外部パートナーと連携しながら、企画・撮影・編集・配信・運用までをトータルに支援できる体制を検討することが推奨されます。
おわりに
動画コマースは、BtoB企業にとって「営業プロセスの変革」と「顧客体験の向上」を同時に実現できる強力な手段です。今後さらに競争が激化する中で、動画活用をいかに戦略的に設計・運用できるかが、差別化の鍵となるでしょう。今こそ、単なる広報手段としての動画から一歩進み、商談獲得・顧客育成を視野に入れた「動画コマース戦略」を構築するタイミングです。
顧客が求める体験価値と、営業・マーケティング部門の業務効率化を両立させる手段として、動画は非常に高いポテンシャルを持っています。これからのBtoBビジネスにおいて、動画の持つ力を最大限に引き出す取り組みが、企業成長の大きな原動力となるでしょう。
「動画マーケティング協会」は、動画制作に関する同業種のお悩み解決のための組織です。
「動画制作、マーケティングに関係する人と繋がりたい!」
「業界の最新トレンドに触れたい!」
「業界の管理体制が知りたい!」
「営業を強化したい!」
こんなお悩みを抱える皆さんはぜひ動画マーケティング協会へ!
▶動画マーケティングについての情報はこちら!
https://vma.or.jp/join