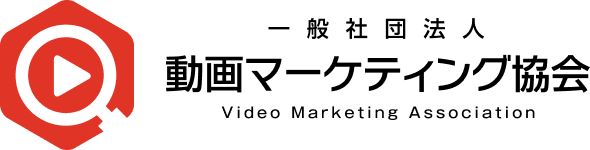はじめに:ライブ配信は“視聴体験”から“購買行動”へ進化中
2025年、企業のマーケティング施策においてライブ配信の重要性がますます高まっています。リアルタイムで視聴者とつながり、その場で双方向のコミュニケーションが生まれるライブ配信は、従来の一方向型広告とは一線を画します。
PR TIMESの調査(2025年5月)では、ライブ配信中に紹介された商品について「購入した」(15.9%)、「検討した」(17.1%)を合わせて3割以上が購買行動に至っており、視聴体験の“瞬間興味”が即座に“行動”へと繋がる構造が明らかになりました。
視聴プラットフォームはYouTubeが85.3%と最多で、Instagram(38.5%)、TikTok(28.2%)も若年層向け施策に有効です。加えて、EC・小売、エンタメ・観光、美容・教育など6割以上の業界でライブ施策が導入されています。
本記事では、最新調査結果に基づき、ライブ配信を活用した販促施策のポイントを体系的に解説します。
第1章:ライブ配信×購買行動 — 数字で見る視聴者の動き

ライブ配信は「視聴者の関心を即購買行動に転換できる点」が最大の魅力です。
PR TIMES調査では、視聴者の約15.9%が配信中に実際に商品を購入しており、17.1%が購入を検討しています。つまり、視聴者の3人に1人以上に“アクション”が発生しているわけです。
この構造の本質は、「生配信だからこそ“今すぐ買いたい”という心を掴める」こと。閲覧だけで終わる通常の動画と異なり、配信中のリアルタイム性と希少性が購買行動を後押しします。
第2章:主戦場はYouTube — プラットフォームの選び方と対策

YouTubeライブの強みは、①蓄積されるアーカイブ性、②検索経由・レコメンド流入の長期性、③収益化や視聴者分析ツールが充実している点です。YouTubeのライブ配信は企業の中長期戦略に向いており、マーケティング体制下での運用に最適です。
一方で、InstagramやTikTokは「日常体験に溶け込む視聴」が主流で、インフルエンサーとのコラボや短期キャンペーンなど短尺・即時訴求に強みがあります。
選び方例
- 企業イベントや製品説明会→YouTube(詳細伝達/蓄積性重視)
- SNS拡散/若年層に訴求した即時性重視施策→Instagram、TikTokなど
第3章:人気ジャンルの現実 — なぜ「音楽・雑談」が強いのか?
データでは、ライブ配信ジャンルで人気なのは「音楽・ライブ」(40.5%)、「雑談・Vlog」(32.1%)であり、販促寄りの「食品・グルメ」(16.3%)、「美容・コスメ」(14.7%)、「アパレル・ファッション」(11.5%)が続きます。
これは、視聴者が「まず楽しみたい」という目的でライブを見ているという証拠です。企業が販促目的で参入するなら、「購入の障壁を下げる設計」が重要になります。
第4章:販促系ライブの課題と工夫 — エンタメ化が鍵
「販促系ライブは習慣化しにくい」と分析しています。よって、購買促進を軸とする企業は、視聴者が楽しめるエンタメ要素を入れ込み、視聴動機を創出する必要があります。
工夫ポイント例
- トーク・インタビュー形式による親しみやすさ
- ゲーム要素(クイズ、リアルタイム投票など)
- ドラマやストーリー性がある構成(Before→体験→After)
こうした形式により「ただ見る」ではなく「参加したくなる構造」を取り入れることがポイントです。
第5章:業種別導入率と成功パターン — 各業界の取り組み

ライブ配信施策の導入率は次の通りです。
- EC・小売:67.5%
- エンタメ・メディア:68.3%
- 旅行・観光:66.7%
- 美容・健康・フィットネス:60.9%
- 教育・オンライン講座:57.1%
これらの業界では、製品の「見せやすさ」やサービスの「体験性」が高く、購買や訴求行動へつなげやすい点が共通しています。
成功事例
旅行会社が現地スタッフの生中継と募集型オンラインツアーをかけ合わせ、参加促進とブランド訴求を同時に実現
美容メーカーがインフルエンサーとのコラボで美容器具の実演ライブを実施、コメントへの即時回答でCVにつながった
第6章:KPI設計のヒント — 「認知拡大」から「購買促進」まで
効果を最大化するには明確なKPI設計が不可欠です。業種・目的に応じて重視すべき指標は異なりますが、以下の視点が参考になります。
- 認知拡大:視聴回数、リーチ数
- エンゲージメント:コメント数、いいね、共有数
- 購買促進:クリック率、コンバージョン率(購入・資料請求等)
- ファン形成・ブランディング:登録者増、リピート率、NPSなど
特に重要なのは「事後評価のためのデータ取得と分析体制」。ライブ配信当日だけでなく、視聴履歴・コメント分析・購買連携などを通して、次回以降の改善につなげるPDCA体制が成果の継続性を支えます。
第7章:ライブ配信運用の体制整備 — 成功に向けた社内準備
ライブ配信の実行力を高めるには、社内体制の拡充が欠かせません。典型的な編成例は以下の通りです。
| 役割 | 担当者 | タスク |
|---|---|---|
| 企画・構成 | マーケ/広報 | 台本作成、コンテンツ構成 |
| 技術・配信 | 動画チーム/外注 | 撮影/配信機材操作 |
| モデレーション | CS/コミュニティ担当 | コメント管理、応対 |
| 解析・改善 | データ担当 | 視聴ログ分析、レポート作成 |
| 司会進行 | MC/社員/ゲスト | スムーズな進行、視聴促進の声がけ |
これらを社内外のリソースで安定稼働させることで、属人的ではない拡張可能な体制が構築できます。
第8章:先行企業の事例紹介 — 成功パターンの実践
美容メーカーA社
インフルエンサーと組んだライブ配信では、商品説明・Q&A・割引クーポンを組み合わせ。視聴者との対話と特典によって、ライブ中の購入率が前年比150%増加。
旅行ブランドB社
現地観光ガイドとの連携生中継+募集型オンラインツアー配信。コメントで質問を受け付け、予約サイトへの導線も設置。半年間で視聴回数は200%増、参加者の満足度も高水準。
BtoB技術商社C社
製品紹介×技術者トーク形式で専門性を魅せる構成。具体的なユースケースや活用方法を示すことで、視聴者からの問い合わせが従来比3倍に。
第9章:今後注目の進化トレンド — テクノロジーと規制に備える
今後のライブ配信施策では、以下の要素も注目されます。
- AI音声吹き替え/字幕生成:多言語対応による海外市場拡張
- リアルタイムOCR/音声解析による自動ハイライト生成
- 視聴後の360度振り返り映像・VR配信の実用化
- 広告規制強化/景品表示法への対応:透明なライブ販促には注意が必要
技術とガイドラインの変化に敏感であることが、先行企業との差を生む鍵になります。
おわりに:ライブ配信を“販促の主戦力”に変えるには

2025年、ライブ配信は視聴体験から購買行動へと直結する「販促の主戦力」へと進化しています。テクノロジーの活用に加えて、社内運用体制・KPI設計・データ分析を含めた全体戦略が成果を分ける時代です。
一過性の配信ではなく、中長期的なPDCAを通じて、自社にとっての「ライブ活用の勝ちパターン」を確立していきましょう。
「動画マーケティング協会」は、動画制作に関する同業種のお悩み解決のための組織です。
「動画制作、マーケティングに関係する人と繋がりたい!」
「業界の最新トレンドに触れたい!」
「業界の管理体制が知りたい!」
「営業を強化したい!」
こんなお悩みを抱える皆さんはぜひ動画マーケティング協会へ!
▶動画マーケティングについての情報はこちら!
https://vma.or.jp/join