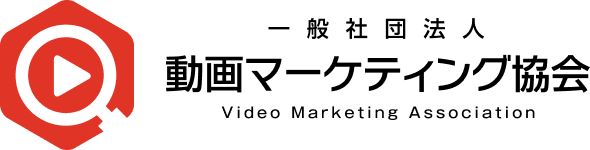はじめに
サントリー『飲みに誘うのムズすぎ問題』が描く、共感とブランド好感度の交差点
短尺動画が当たり前となった今、広告に求められているのは「共感を生み、行動を促す力」です。2025年のYouTube Works Awardsで「Best Brand Lift部門賞」を受賞した、サントリーホールディングスの動画広告『飲みに誘うのムズすぎ問題』は、その象徴的な成功事例と言えるでしょう。
本記事では、この作品に込められたクリエイティブ戦略や共感設計、ブランド価値向上への貢献、さらにはBtoB企業における応用の可能性までを、動画マーケティングの視点から詳しく解説します。
第1章: 「飲みに誘う」ことすら、気を遣う時代
動画は、職場で若手社員が同僚に飲みに行こうと声をかけようとするも、気を遣いすぎて結局言い出せない様子を描いています。繰り返される視線のやりとり、沈黙の時間、心の声と表情のズレ。何気ないやりとりの中に、現代の人間関係における“温度差”や“遠慮”が込められています。特にZ世代を中心に、コロナ禍以降の非対面コミュニケーションが常態化したことで、「断られたら気まずい」「嫌がられたらどうしよう」という心理的ハードルは一層高くなっています。視聴者は、主人公の気持ちに深く共感し、「あるあるすぎる」とSNSでも話題に。

第2章:サントリーが描いたのは、商品ではなく“行動の手前”
この動画における最大の特徴は、飲料そのものを訴求していないことです。描いているのは「飲みに行くこと」の前にある気持ちの揺らぎや言い出しにくさ。つまり、「消費行動を後押しする感情」に焦点を当てています。
最終的には「もう少し勇気を出して声をかけてみようか」という余韻のあるメッセージで締められ、企業ブランドが共感し、寄り添う存在として印象づけられています。
これは、単なる商品のプロモーションから、ブランドのパーパス(存在意義)を表現する広告へと進化した好例であり、企業広告が生活者との接点を持つ手法の変化を象徴しています。
第3章:なぜ「Best Brand Lift部門賞」を受賞できたのか?
YouTube Works Awardsの審査基準の一つである「ブランドリフト(Brand Lift)」とは、広告視聴前後での認知・好感度・購入意向などの変化を測定するものです。
本動画は、視聴後に「サントリーに好感を持った」「親しみやすさを感じた」という視聴者が顕著に増えた点が評価されました。商品の露出が最小限でありながらも、高い共感性と感情訴求によってブランドとの心理的距離を縮めることに成功していたことが、大きな要因です。
広告であるにもかかわらず、「サントリーの優しさが伝わる」「押しつけがましくない」といった声がSNS上にも多数投稿されており、広告への信頼感そのものを構築できたことが、まさに現代型ブランディングの成果と言えるでしょう。

第4章:「誘いにくさ」は、BtoBにも共通する“心理”
このテーマは、BtoCだけでなくBtoB領域にも応用可能です。たとえば営業現場では、
- ・「このタイミングで再アプローチすべきか迷う」
- ・「DMやフォローアップの送信にためらいがある」
- ・「距離感を間違えると関係が壊れるかもしれない」
といった“声をかけること”への心理的障壁が存在します。
本動画のように、こうした行動前の逡巡を可視化する動画は、営業や採用、社内コミュニケーションにおいても強い共感を生み、企業としての「人間味」や「思いやり」を伝える手段になり得ます。
たとえば、
- ・「初回訪問がしにくい営業の本音」
- ・「上司に声をかけづらい若手の気持ち」
- ・「中途入社者がチームに溶け込むまでの不安」
といったテーマを、コミカルかつリアルに描いた動画は、BtoB企業の文化発信・インナーブランディングにも効果を発揮するでしょう。
第5章:「押しつけない広告」が選ばれる時代に
従来の広告は、「どう見せるか」「何を伝えるか」が中心でした。しかし今は、「どう寄り添うか」「どう共に歩むか」という視点が重視されています。
その中で本作のように、生活者の心の奥にある「不安」や「戸惑い」に焦点を当てる手法は、ますます有効性を増しています。これは、社内コミュニケーションや採用広報でも同じです。
「答え」ではなく「共感」を届ける動画こそ、視聴者の記憶と行動を変える力を持つのです。

第6章:動画表現だからこそ伝わる「沈黙」の価値
『飲みに誘うのムズすぎ問題』では、主人公のセリフは非常に少なく、物語の大半を“沈黙”や“間”が占めています。この演出は、映像ならではの表現手法であり、テキストや静止画では伝わらない“空気感”を醸し出しています。
このような間の演出によって、視聴者は主人公の葛藤や緊張を自分の経験に重ねて自然と感情移入しやすくなるのです。言葉に頼らず、視線の動きやわずかな表情の変化で感情を伝える手法は、動画の本質的な強みであり、ビジネス動画でも応用可能です。
第7章:感情設計から成果設計へ──マーケターに求められる視点の転換
サントリーの本動画が評価された理由の一つに、感情的共感とマーケティング成果の両立があります。単なるイメージ向上にとどまらず、広告視聴後のブランド好感度や再生完了率、視聴後行動(クリック・検索など)といったファネル全体にポジティブな影響を及ぼしている点が、データでも示されています。
このような成功事例からは、今後のマーケターにとって以下の視点がより重要になることが見えてきます:
- ・「誰に響かせたいか」ではなく「どう感じてもらいたいか」を起点に設計する
- ・「売るために動かす」のではなく「寄り添って行動を後押しする」姿勢をとる
- ・「成果」を定義する際に、数値的なKPIだけでなく感情の変化を含める
このような発想の転換は、特に採用動画・ブランディング動画・IRや社内広報向け映像で大きな差を生みます。
第8章:今後の展望と企業動画のヒント
『飲みに誘うのムズすぎ問題』がもたらした最も大きな気づきは、「ちょっとした感情のひだ」が動画表現の起点になり得るということです。
BtoBにおいても、たとえば以下のようなテーマを取り上げることで、従来にない共感型コンテンツが生まれるでしょう:
- ・取引先への返信に迷う若手営業の心理
- ・新しいチームに馴染めずに悩む異動直後の社員
- ・提案書を出す前夜に感じる「本当にこれでいいのか」という不安
これらは商品説明や実績紹介では届けられない、「人間」を感じさせるストーリーです。企業がこうした動画を通して“感情のリアル”を発信することで、取引先・求職者・社員からの信頼と愛着を醸成できる時代が訪れているのです。
終わりに:動画は「伝える」から「気持ちに寄り添う」時代へ
サントリーの『飲みに誘うのムズすぎ問題』は、「誘う」という行為に潜む人間的な揺らぎに焦点を当て、それをユーモアとリアルを交えて表現した秀逸な作品です。
単にプロダクトを売り込むのではなく、生活者の行動前夜に寄り添う。このスタンスが、多くの視聴者の共感とブランド好感度の向上に直結したことは、あらゆる企業にとってのヒントになるはずです。
動画マーケティング協会では、企業の動画活用を戦略的にサポートする情報と機会を提供しています。
- ・「感情に届く動画を企画したい」
- ・「広告効果を定量化して社内に示したい」
- ・「他業種の成功事例を参考にしたい」
そんな皆様は、ぜひ当協会にご参加ください。
▶ 詳しくはこちら:https://vma.or.jp/join